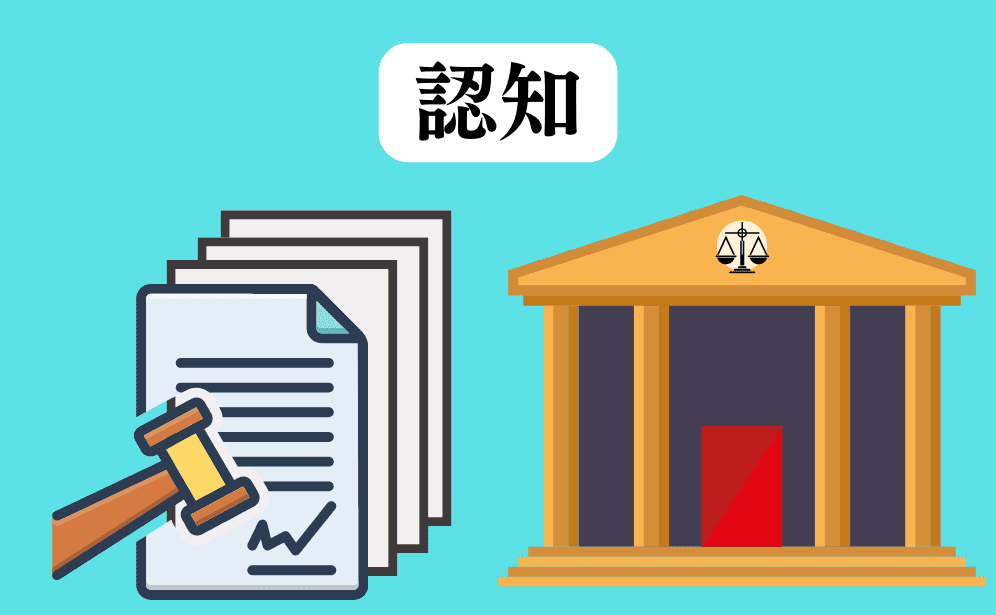認知は相続に関係するので、親族間で争いになることがあります。
なぜなら、認知が認められると相続人が増えますし、逆に認知が無効になると相続人が減るからです。
※相続人の順位が変更する可能性もあります。
そのため、認知に関する最高裁の判例も多く残っています。
- 認知の届出に関する判例
- 認知の訴えに関する判例
- 認知無効の訴えに関する判例
今回の記事では、認知の判例について説明しているので、認知の悩みを解決する際の参考にしてください。
目次
1.認知の届出に関する判例
まずは、認知の届出に関する判例を説明していきます。
認知者の意思に関する争いと、認知届が別の届出としての効力を有するかで争っています。
1-1.認知者の意思と認知届の関係
認知届と認知者の意思に関する判例を2つ説明します。
認知届が無効とされた判例
認知者の意思に基づかない届出による認知は、認知者と被認知者との間に親子関係があるときであつても、無効である。
認知の届出が認知者の意思に基づいていなければ、認知者と被認知者(子ども)に親子関係があっても、認知は無効となります。
ただし、実際に親子関係があれば、認知の訴えは可能です。
認知届が有効とされた判例
甲、乙間に血縁上の父子関係があり、甲が乙を認知する意思を有し、かつ、甲から他人に対し認知届出の委託がされていたときは、届出が受理された当時甲が意識を失つていたとしても、その届出の前に翻意したなど特段の事情のない限り、右届出の受理により認知は有効に成立する。
認知者に被認知者(子ども)を認知する意思があれば、認知届が受理されたときに認知者が意識を失っていても、認知は有効となります。
1-2.出生届を認知届とした判例
出生届が認知届としての効力を有するとされた判例です。
嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によつて受理されたときは、その各届は、認知届としての効力を有する。
父親が自分の嫡出子または非嫡出子として子の出生届を提出すると、出生届は認知届としての効力を有します。
父親が自分の子であると意思表示をして出生届を提出している以上、認知届と変わらないという判断です。
1-3.認知届は養子縁組届にならない
認知届と養子縁組に関する判例です。
認知の届出が事実に反するため無効である場合には、認知者が、被認知者を自己の養子とすることを意図し、後日、被認知者の母と婚姻した事実があるとしても、右認知届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。
認知届が事実に反するため無効だからといって、認知届を養子縁組届とみなすことはできません。
認知は単独行為ですが、養子縁組の成立には当事者の合意が必要です。たとえ被認知者の母親と結婚しても養子縁組は成立しません。
2.認知の訴えに関する判例
次は、認知の訴えに関する判例を説明していきます。
認知の訴えに関する判例は、大きく分けると2つあります。
- 認知の訴えの提起に関する判例
- 認知の訴えの期間に関する判例
それぞれ説明していきます。
2-1.認知の訴えの提起に関する判例
認知の訴えの提起に関しては、「誰が」できるのかを争っています。
未成年者の法定代理人は認知の訴えを提起できる
未成年者の法定代理人は、子に意思能力があっても、法定代理人として認知の訴えを提起できます。
未成年の子の法定代理人は、子に意思能力がある場合でも、子を代理して、認知の訴を提起することができる。
法定代理人は子に意思能力がない場合だけでなく、意思能力がある場合でも認知の訴えは可能です。
戸籍の訂正を待たなくても認知の訴えは提起できる
戸籍の訂正を待たなくても、実親に対して認知の訴えを提起できます。
父母でない者の嫡出子として戸籍に記載されている者は、その戸籍の訂正をまつまでもなく、実父又は実母に対し認知の訴を提起することができる。
上記の判例は、戸籍の記載が間違っている場合です。
戸籍の訂正が済む前であっても、認知の訴えは提起できるとしています。
嫡出推定を受ける子は認知の訴えを提起できない
民法の規定により嫡出の推定を受ける子は、認知の訴えを提起できません。
民法七七二条による推定を受ける摘出子は、他に実父がいる場合であつても、同法七七四条ないし七七八条に定められている摘出否認の訴によつてその推定が覆えされないかぎり、実父に対して認知の訴を提起することはできない。
嫡出の推定を受ける子は、先に嫡出否認の訴えを提起して、嫡出の推定を覆す必要があります。
認知請求権は放棄できない
子の父に対する認知請求権は放棄できないとした判例です。
子の父に対する認知請求権は放棄することができないものと解するのが相当である。
認知を長期間請求しないからといって、請求権を放棄したことにはなりません。
2-2.認知の訴えの出訴期間に関する判例
認知の訴えは父の死亡から3年経過すると提起できません。
関連記事を読む『死後認知とは父親が亡くなった後に認知を請求する手段』
父の死亡を知った日から3年経過前でも提起できない
父の存在と死亡を知った日から3年経過していなくても、認知の訴えは提起できないとした判例です。
父の死亡の日から三九年一か月後に提起された認知の訴えは、当該父の存在及びその死亡の事実を知つた日から三年を経過していないという事情があつても、不適法である。
認知の訴えを提起できる期間(3年以内)は、平等に適用されます。
たとえ父の存在や死亡を知ってから3年経過していなくても、認知の訴えは提起できません。
父の死亡から3年経過しているが提起できる
父の死亡から3年経過しているが、特別な事情を考慮して認知の訴えを提起できるとした判例です。
父の死亡の日から三年一か月を経過したのちに右死亡の事実が子の法定代理人らに判明したが、子又はその法定代理人において父の死亡の日から三年以内に認知の訴えを提起しなかつたことがやむをえないものであり、また、右認知の訴えを提起したとしてもその目的を達することができなかつたことに帰すると認められる判示の事実関係のもとにおいては、他に特段の事情がない限り、民法七八七条但書所定の認知の訴えの出訴期間は、父の死亡が客観的に明らかになつた時から起算すべきである。
特別な事情を説明すると、父親が生死不明になった後で、母親が婚姻届けを提出しています。婚姻届け提出後に子を出生しているので、子は父親の嫡出子です。
ですが、父親の死亡が確認されたことにより、父親と母親の婚姻関係も無効となり、子と父親の親子関係も無効となりました。親子関係が無効になった時点で、父親の死亡から3年経過していたという事情です。
上記の判例は事情が特殊なので、参考にする際は注意してください。
3.認知無効の訴えに関する判例
最後に、認知無効の訴えに関する判例を説明します。
3-1.認知をした父も認知無効の訴えを提起できる
認知をした父も利害関係人として、認知無効の訴えを提起できるとした判例です。
認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。
たとえ血縁上の父子関係がないことを知って認知した場合でも、父は認知無効の訴えを提起できます。
関連記事を読む『認知の取り消しは原則として認められないが無効の主張は可能』
3-2.認知無効確認請求権は一身専属権である
父親が原告になっていた認知無効確認請求訴訟の継続中に死亡すると、訴訟は終了するとした判例です。
父が原告となつて追行していた認知無効確認請求訴訟の係属中に、原告が死亡したときは、該訴訟は終了する。
認知無効の訴えは、請求権者の一身に専属する権利なので、相続の対象になりません。
したがって、請求権者が訴訟中に死亡すると、訴訟は終了となります。
3-3.韓国の出訴期間経過後でも認知無効の訴えを提起できる
韓国の出訴期間を経過している場合でも、認知無効の訴えを提起できるとした判例です。
大韓民国の国籍を有する者から認知された日本国の国籍を有する者は、大韓民国民法の規定する出訴期間を経過した後においても、認知無効の訴えを提起することができる。
父親が韓国籍で子が日本国籍なら、子は日本の法律により認知無効の訴えを提起できます。
3-4.認知後数十年経過していても認知無効の訴えを提起できる
認知後50年以上経過してから認知無効の訴えを提起しても、権利濫用には当たらないとした判例です。
認知者が被認知者を不憫に思い、自分の子として認知の届出をし、長年自分の家業を手伝わせていたところ、認知者の実子が事実上の婿養子と結婚したころから被認知者と認知者、その妻、実子との間が円満さを欠くようになり、認知者の死亡直後、被認知者が家庭裁判所に対し、遺産分割の調停の申立をしたなどの判示の事実関係のもとでは、認知者の妻であり、かつ、被認知者の実母である者及び認知者の実子から被認知者に対してされた認知無効確認の請求は、それが認知後五十数年を経過し、かつ、認知者の死亡後であつても、権利の濫用にあたるとはいえない。
上記の事例は、認知者(父親)の死亡後に、被認知者(子ども)の母親と認知者の実子が認知無効の訴えを提起した。
親子関係がないと知って50年以上経過していても、認知無効の訴えは権利濫用には当たらないと判断しています。
3-5.認知の判決確定後は第3者も無効を主張できない
認知の判決が確定しているなら、第3者も認知無効の訴えを提起できないとした判例です。
認知の判決が正当な当事者の間に確定している以上、該判決は第三者に対しても効力を有するから、これに対し再審の手続で争うのは格別、もはや第三者も反対の事実を主張して認知無効の訴を提起することはできない。
認知の確定判決がある場合には、第三者は民法第七八六条により反対の事実を主張して認知無効の訴を提起することはできない。
認知の判決が確定すると第3者に対しても効力を有します。
ですので、認知の判決確定後は、第3者も認知無効の訴えを提起できません。
4.さいごに
今回の記事では「認知に関する判例」について説明しました。
認知は相続に関係するので、昔から争い(訴訟)になりやすいです。
そのため、認知に関する最高裁の判例も多く存在します。
- 認知の届出に関する判例
- 認知の訴えに関する判例
- 認知無効の訴えに関する判例
重要な判例も含まれているので、認知(相続)について調べているなら参考にしてください。